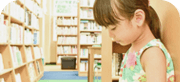大規模 大学図書館の課題
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
大規模な大学図書館の定義
大学の規模については、大規模・中規模・小規模の3つにわけることができます。
大学の規模は主に収容定員の数によって定められており、大規模な大学とは「収容定員が8,000人以上」の大学※となります。
そのような大学にある図書館が、大規模な大学図書館です。
大学図書館としての大まかな定義は、蔵書数 100万冊以上、職員数(業務端末数)50名以上の図書館です。
※参照元:旺文社教育情報センター https://eic.obunsha.co.jp/viewpoint/201602viewpoint/#:~:text=28年度~30年度,3つの規模に分ける。
大規模大学図書館の特徴
大規模大学図書館の大きな特徴の一つが、利用人数と蔵書数の多さです。日常的に多くの利用者が来館し、図書の貸出や返却、レファレンスサービスの申し込み、ILL(図書館間相互利用)サービスなど、用途にあわせて様々なかたちで図書館を利用しています。
大規模大学は学部などによって複数のキャンパスにわかれていることが多く、学部にあわせた蔵書やサービスなど、キャンパスごとに特色のあるのが大規模な大学図書館の特徴でもあります。
図書館業務の特徴
職員数が多く、係が細分化されているため、それぞれの職員の業務範囲が明確なことが特徴です。
また、業務委託をしている場合が多く、正職員は実業務よりも管理的な立場に立ち、「実務業務は業務委託に任せる」といったように役割をはっきり分担しています。
システム管理の特徴
大学自体が大規模であるため、システムを部門ごとに管理することが多く、図書館システムは図書館で管理する必要があります。学内のシステムとの連携を図る場合、学内調整に時間がかかる場合があります。
大規模大学図書館システムの運営課題
図書館業務の運営課題
全業務を把握している人がいないことが大きな課題です。
職員数の多い大学図書館では、管理的な立場の正職員と、実務を行う業務委託職員に分かれ、かつ係が細分化されています。
その結果、各々の職員は担当の業務を行えるものの、職員が全業務を把握することが難しくなっています。
システム管理の課題
システム面では、大学自体が大規模である故の課題として
- システム管理を部門ごとに行うため、図書館システムの運用についても情シスには頼れない。
- 学内の各部門との調整に時間がかかり、システム連携ができていない。
があります。
図書館に関わる人が多い大規模大学図書館では、業務の係や身分によって設定するアクセス権限の管理が複雑になりやすく、様々なパターンの利用者と業務を想定する必要があるため、システムも複雑になりがちです。
こういった複雑なシステムを構築、運用するためには、カスタマイズ費用や保守費用が高額になる傾向にあります。
また独自のカスタマイズで複雑になったシステムは、最新のサービスやバージョンアップを受けられない場合があることも注意が必要です。
図書館システム・会社一覧と
選び方のポイント
図書館システム移行で解決できる課題
大規模大学図書館は、その規模の大きさから、システム全体が複雑になりやすく、システム管理や、関係各所との調整連携で図書館にかかる負担は、業務面でもコスト面でも大きくなりがちです。
システム面での負荷削減には、サーバーやシステム管理の業務から解放される、クラウド型の図書館システムの導入が解決の近道です。
学内のシステムと速やかに連携することで、図書館内でのシステム管理や業務負荷が削減につながります。
また、複雑になりがちなシステムを図書館システムベンダーの提案を受けることで、シンプルな運用にすることもできるでしょう。
最新サービスや、バージョンアップをつねに受けられるシステムを選んでおくと、システムの運用開始後にベンダー頼りにならず、セキュリティや、OS,連携するシステムの変更にも柔軟に対応できます。
規模や課題によって変化する大学図書館に求められる機能と役割。自館の「課題」と「ビジョン」とともに進化できる、変化に強い図書館システムを選びましょう。
ニーズに合った実績とサービスで選ぶ
大学図書館システム3選
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。