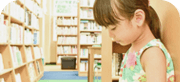図書館システムのOPAC
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
図書館システムのOPACとは?
OPACは、利用者がオンラインで図書館の蔵書目録を検索・閲覧できるシステムです。「Online Public Access Catalog」の略称で、「オーパック」または「オパック」と呼ばれます。書誌や所蔵の情報が電子化されているため、コンピュータ上で検索できます。
現代の図書館において、OPACは蔵書検索と利用者サービスの中核を担っています。デジタル化を推進して、利用者の利便性と図書館の業務効率を向上させるために重要です。
OPACの歴史と発展
コンピュータが普及する前の図書館では、紙の目録カードを使用して蔵書情報を管理していました。書誌や所在などの情報を記載したカードを書名順や著者名順、分類順に整理し、カードボックスに保管する方式が一般的でした。
1980年代からコンピュータが普及するとOPACシステムも開発され、図書館サービスは大きな進歩を遂げました。初期のOPACは、館内の専用端末でのみ利用できました。現代では、インターネットの普及により館外からも24時間アクセスできる「Web型のOPAC」が主流となっています。
図書館システムの歴史については以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
図書館システムの歴史
OPACの未来展望
現在のOPACシステムは、従来の検索機能に加えて、利用者の利便性を向上させる様々な機能を搭載しています。AIを活用したレコメンデーション機能やデジタルコンテンツとの連携など、図書館サービスはさらなる進化を遂げています。図書館司書の役割も、OPACの技術革新とともに変化してきました。
図書館システムのOPACの機能
基本的な検索機能
OPACの中核となるのは蔵書検索機能です。利用者は以下の方法で図書館資料を検索できます。
- 書名検索: 図書のタイトルから該当資料を検索する
- 著者名検索: 著者名や編者名を指定して検索する
- 件名検索: 主題や内容に基づいて検索する
- 分類検索: 日本十進分類法などの分類体系に基づいて検索する
- キーワード検索: 複数の検索語を組み合わせて横断的に検索する
予約・取り置き機能
現代のOPACシステムでは、検索した資料の予約や取り置きを行うことも可能です。貸出中の資料に対する予約の申込みや他図書館からの取り寄せの依頼など、利用者のニーズに応じた柔軟なサービスを提供します。
マイライブラリ機能
利用者個人の貸出履歴や予約状況を管理する「マイライブラリ」機能もあります。利用者自身がオンラインで、現在借りている資料の確認や返却期限の延長手続きなどができる機能です。
デジタルコンテンツ連携
近年のOPACでは、電子書籍やデータベースなどのデジタルコンテンツとの連携も進んでいます。紙媒体の図書とデジタルコンテンツを統合的に検索し、利用者ごとに適した情報資源の収集が可能です。
利用統計・分析機能
図書館管理者向けの機能として、利用統計・分析機能も備えています。「どの資料がよく利用されているか」「どのようなキーワードが検索されているか」などのデータを収集し、蔵書やサービスの改善に活用できる機能です。
OPAC以外にも図書館システムの基礎知識をチェックしよう
図書館システムのOPACは、現代の図書館サービスに欠かせない基盤システムです。利用者の情報アクセスの利便性と図書館の業務効率化を同時に促進するために、OPACの役割と機能を理解することが欠かせません。
OPAC以外にも、図書館システムの選定や導入を検討するために理解しておかなければならない情報があります。以下のページに図書館システムの基礎知識をまとめてありますので、ぜひ参考にしてみてください。
図書館システムとは
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。