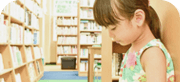図書館システムにおけるオンプレミスとクラウドの違いとは
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
図書館では、選書や収集、図書整理や蔵書データ分析、蔵書点検など様々な業務が行われています。これらの膨大な業務を効率化する図書館システムには、オンプレミス型とクラウド型の2つのシステムパターンが存在します。
オンプレミスとクラウドにはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、それぞれのシステムのメリットやデメリット、両者の性能や操作性の違いなどを網羅的に紹介していきます。
オンプレミスとは
オンプレミスとは、自社内もしくはデータセンターのサーバーに情報システムをインストールして利用する形態を指します。基本的にオンプレミスは非公開または利用者限定のサービスにおいて利用されます。
オンプレミスは、具体的には自社でのみ使用する業務システムや機密情報を扱うシステム、メールサーバーやWeb会議システム、個人情報を取り扱うシステムなどを利用する際に導入されます。
メリット
自由度が高く図書館に合ったシステムを構築できる
図書館システムというアプリケーションだけでなく、ハードウェアやOS、ミドルウェアなどは、導入環境や予算などに合わせて選定可能。もちろん、図書館システムの仕様策定も担当職員の業務や図書館利用者のニーズなどをとりまとめて、自由度の高いシステム構築もできるでしょう。
高度な外部システムとの連携が可能
図書館システムをオンプレミスで稼働させる場合、利用者データベースとの接続を特定ネットワーク内で完結できるため、インターネット経由でのデータ連係よりはセキュリティリスク対策になるでしょう。それ以外でも図書館システムを外部システムと連携させる場合、必要に応じた制限をかけるといった構築ができます。
サービス停止のリスクをコントールしやすい
世界トップクラスのIT企業が提供するクラウドサービスでも、サービス停止のトラブルは起きるもの。リスク対策という意味では、オンプレミスでもノートラブルにはできないものの、トラブル時に自らが関与できますし、メンテナンスのタイミングもコントロールできます。
デメリット
初期費用が高額でサービスインまでの時間もかかる
オンプレミスだとハードウェアやネットワーク環境、基本的なサーバーアプリケーションのセットアップなどの初期費用がかかります。動かすシステムの規模にもよりますが、高速処理や安定稼働などを考慮すれば、高額になるケースも珍しくありません。また、図書館システム自体はパッケージタイプでも、各種設定作業などもクラウドよりは時間がかかってしまいます。
メンテナンスは自己責任で、費用も手間もかかる
運用フェイズでは、図書館システムはベンダーがサポートしてくれる製品もありますし、インフラはアウトソーシングも可能です。ただし、トラブル時は自分たちが主導して対応しなくてはなりませんし、予期せぬ出費リスクもあり。また、ハードウェアやサーバーOSなどは適時アップデートすることになりますが、その際にかかる改修コストが大きくなるケースもあります。
クラウドとは
クラウドとは、クラウドベンダーが用意したシステムをネットワーク経由で利用するサービスであり、有料のサービスや無料のサービスがあります。サーバーやパッケージソフトなどを自社で保有しないので手軽に利用できる特徴があります。操作性も高く利用しやすいため、ITスキルがそれほど高くない方でも利用しやすいものが大半だと言えます。
身近な例としてGメールやGoogleドライブ、Yahooメール、ワードプレスなどもクラウドサービスに含まれます。
メリット
システム導入時の費用や時間をセーブできる
クラウドの図書館システムなら、ベンダー側がインフラ及びWebアプリケーションなどトータルで提供してくれるので、導入する図書館に合わせた設定やカスタマイズをすることはあっても、導入時のコストや時間などはオンプレミスよりも大幅に抑えることができます。
インラフのメンテはお任せしつつ、冗長性に優れる
クラウド型のサービスは一般的にメンテナンス全般をベンダー側にお任せできます。図書館側は業務に専念すればOK。機能追加やバージョンアップも月額利用料に含まれることが珍しくありません。利用者数が増えた場合にプラン変更がしやすいソリューションもあり、冗長性に優れているのもクラウドのメリットです。
標準的メンテナンスによるサービス停止を回避できる
クラウドなら、365日24時間サービス停止せずに運用可能なサービスもあります。オンプレミスの場合、一定頻度でのメンテナンスはリスク対策としても必須であり、メンテナンスせずノンストップで運用するならシステムの冗長化が必要で、コストアップにもなってしまう分、クラウドの方が有利といえます。
デメリット
サービスによって自由度はある程度制限を受ける
クラウドの図書館システムでもカスタマイズ対応可能なソリューションもありますが、対応可能な範囲は限られます。業務フローなど、ある程度はシステム側に合わせて運用を変えなくてはならなくなるケースはあるでしょう。また、インターネット経由での接続が基本となるため、外部システムとの連携が難しくなることもあります。
トラブル時に図書館側ではハンドリングできないケースも
日常的なメンテナンスは図書館システムのベンダー側にお任せできるのですが、万が一トラブルが発生した場合、復旧やリカバリーもベンダー次第となってしまいます。サービス停止や情報漏洩などの深刻なトラブルが起きた時、図書館として詳細な状況把握や対応指示ができない面もあることは知っておいた方がいいでしょう。
どこが違うのか
オンプレミスとクラウドは具体的にどこが違うのでしょうか。ここでは導入時におけるコストの違いや運用の際の違い、操作性やセキュリティなど両システムの代表的な違いを紹介していきます。
初期費用
初期費用は、多くの場合オンプレミスは割高になる一方で、クラウドは比較的安く抑えることができます。
具体的には、オンプレミスはサーバー機器や回線、ソフトウェアライセンス、設定費用などのコストがかかり、金額として数百万円以上かかるのが通常です。サービス料金は一般的に月額であり、固定費で計上されるため予算化しやすいメリットがあります。
一方クラウドサービスはサーバー機器の購入は不要であり初期費用をほとんどかけることなく利用できます。一般的にクラウドサービスの料金は月額制ですが、使用する量で変動するため月によっては高くなる場合もあります。
ランニングコスト
オンプレミスのランニングコストですが、サービス料金は一般的に月額制となっています。固定費で計上されるため予算化しやすいメリットがあります。しかしメンテナンスやセキュリティなど、利用開始した後にも適宜コストが発生します。
クラウドの利用料金は月額制が一般的ですが、多くのシステムでは使用する量で変動する従量制を採っています。そのため、月によってはランニングコストが高くなる場合もあります。ただしシステム管理はクラウドベンダーが行うため、利用料金以外のランニングコストは安く抑えることができます。
導入までの期間
オンプレミスでは、システムを導入するにあたりサーバー機器や回線、各種ソフトウェアを自社で用意する必要があります。そのため調達から導入までに相応の時間がかかるのが一般的です。ビジネスで利用するのであればできるだけ早い段階で必要なものを用意して、準備に時間をかける必要があるでしょう。
クラウドの場合は、システムを申し込み決済が終わればすぐに導入することが可能です。オンプレミスと比べて機動性が高く、導入決定から早い段階で導入することができます。
カスタマイズ性
オンプレミスは、システムの管理を自社が担っているためカスタマイズ性は高く、自社のサービスの内容に沿ったシステムを構築できます。基本的に利用できないサービスはなく、自由度はかなり高くなります。
一方でクラウドは、ベンダーがシステムの管理を担っているためカスタマイズ性は低く、中には利用できないサービスもあります。自社でシステムを占有できないため自由度は大きく損なわれます。
セキュリティ
オンプレミスの場合、セキュリティに関する責任は自社が負うのが一般的です。サーバーやファイアウォール、侵入検知システムといったセキュリティ機器類は全て自ら用意する必要があります。
また、セキュリティ対策の一環であるOSやミドルウェアのバージョンアップもユーザー自ら行わなければなりません。したがってセキュリティ対策に手間がかかる特徴があります。
クラウドサービスでは、基本的なセキュリティ機能は開発ベンダーから提供されます。基本的にユーザー企業がソフトウェアに対するセキュリティ対策を取る必要はなく、クラウド自体のセキュリティは開発ベンダー側が責任を負います。ただし、クラウドで取り扱うユーザーデータやID、パスワード、クライアントデータなどはユーザー側が責任を負うため、これらの情報セキュリティはユーザー自身が行う必要があるので注意が必要です。
図書館システム・会社一覧と
選び方のポイント
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。