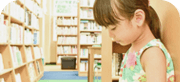海外で普及が進む電子図書館
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:2022年8月4日
|更新日:
2024年11月27日
データベースの中に大量の書籍データを蓄積し、そのデータを貸し出すという形態をとっている電子図書館。近年では、海外でこの電子図書館が急激に普及しています。ここでは、そんな電子図書館の概要やメリット・デメリットを見ていきましょう。
電子図書館とは?
電子書籍の概要
電子図書館とは、電子書籍を通常の図書館と同じように貸し出すというサービスです。データベース内に、各種書籍や雑誌はもちろんのこと、音源や映像媒体などさまざまなデータを格納し、ユーザーはそれらを自由にインターネット経由で貸し出しという形で利用できるのです。
貸出業務の電子化と閲覧の電子化
「電子図書館」と言った場合、そのサービス内容は「貸出業務の電子化」「閲覧の電子化」のふたつに別れます。
「貸出業務の電子化」は、従来の貸出業務を電子化するというものです。紙の図書の貸し出しを受けると、利用者は図書館によって定められた期間その図書を独占的に読むことができ、返却期限までに図書館に返却する、というのが従来の図書の貸出業務です。電子図書館では、この業務が電子化されます。すなわち、利用者には対象となる電子図書館が収蔵する電子書籍を閲覧する権利が期間限定で与えられ、貸し出し期限が来ると自動的にその電子書籍は読めなくなります。
「閲覧の電子化」は、特に返却期限を設けず、利用者が電子書籍のデータベースの中から自分の探している書籍を検索・発見して閲覧するというもの。主に大学図書館向けの電子図書館サービスがこの形態をとっています。「貸出業務の電子化」が「読書」を目的として利用されるものであるのに対し、「閲覧の電子化」はレポート作成のために書籍の中の必要な箇所を確認したり、気になった箇所をコピー&ペーストして次の電子書籍の検索キーワードにしたりするといったような「利用」を前提としたサービス運用を意識しているのが特徴です。
海外の電子図書館事情
日本に比べると、海外は電子図書館の普及が圧倒的に進んでいます。その中でも、特に電子図書館サービスが充実しているのがアメリカです。アメリカ公立図書館は、ここ数年で貸出用の電子書籍の数を大幅に増やしており、書籍購入予算の中の実に20%を電子書籍に充てているのです。ほかにも、Toronto Public Library(トロント公共図書館)では、2017年における電子書籍の貸出冊数が前年に比べて19%アップ、オレゴン州にあるMultnomah County Library(マルチノー郡図書館)では、前年比で電子書籍の貸出数が28%アップ※1 したと報じられており、今後も電子図書館サービスは拡大していくと見られています。
また、アメリカでは電子図書館サービスに参入する企業も増えてきました。たとえば、OverDrive社という企業は、58箇所の電子図書館と提携しており、それらの図書館における電子書籍の貸出数は100万冊を超えたと報じられました。※2
アメリカ以外で電子図書館サービスが普及している国としては、シンガポールが挙げられます。シンガポールでは2009年から電子書籍の貸し出しを行っていますが、その貸し出し数はサービス開始当初から300万件にものぼっています。さらに2014年には貸出数は1100万件という数字を叩き出しました。シンガポールの図書館全体における紙の本の利用者数は、およそ3400万件となっているので、2014年のこの数字は、実にその3分の1近くに迫っていると言えるのです。※3
※1※2 参照元:GOODEREADER(https://goodereader.com/blog/e-book-news/58-libraries-loaned-out-over-1-million-ebooks-in-2017)
※3 参照元:HON.jp(http://hon.jp/news/1.0/0/6658)
日本国内の電子図書館事情
日本国内における電子図書館サービスは、まだまだ十分に普及しているとは言えません。しかし、知名度は低いものの数カ所利用を開始しているところがあります。日本で最初に電子図書館サービスを開始※1 したのは、千代田区立図書館。利用可能な人は「東京都千代田区に在住または通学・通勤している人のみ」とかなり限定されてはいるものの、千代田区立図書館にて利用者登録を済ませれば、インターネットを通していつでも電子書籍を最大5点まで借りることができるようになっています。読み終わった電子書籍は、画面上の返却ボタンを押すだけで返却できるので、紙の本のように図書館まで出向いて返却する必要がありません。返却ボタンを押すのを忘れていても、返却期限の2週間を過ぎれば自動的に返却されるので、返却し忘れの心配もないのです。
前述の通り、日本国内では電子書籍サービスはまだ十分に普及しているとは言えません。そのため、貸し出し可能な電子書籍も、およそ8000冊※2 とまだ十分な数はそろっていない状態です。しかし、今後の貸し出し可能な電子書籍の拡充は十分期待できるでしょう。また、電子書籍ならスマホやパソコンで場所や時間を問わず利用できるので、若者の本離れの防止や、手軽に拡大しながら読めることからお年寄りでも本を読みやすい環境を提供できると言ったメリットも注目されているのです。
※1 参照元:日経XTECH(https://xtech.nikkei.com/it/article/NEWS/20071112/286953/)
※1 参照元:千代田区立図書館 公式HP(https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/information/20160227-17056/)
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
電子図書館のメリット
運営側のメリット:在庫管理のコストの大幅減少
電子図書館には、運営側のメリットもあります。従来の図書館とは異なり、電子書籍なら蔵書を保管するための物理的スペースが必要ありません。さらに現物管理の手間や貴重な資料の紛失や汚損の危険、長期間の保管による劣化問題などが一気に解消するので、書籍の維持管理コストが大幅に削減されるのです。
利用者側のメリット:365日24時間いつでも利用可能
電子図書館の最大のメリットとも言える点が、365日24時間いつでも、時間に縛られずに利用できることでしょう。閲覧だけでなく貸し出し・返却もいつでもできるので、図書館にわざわざ行く必要がなくなりますし、貸出期間が来れば自動的に返却されるので返却し忘れの心配もありません。さらに、貸し出しや返却の際に大量の本や重い辞典などを持って図書館と自宅を行き来する労力も必要なくなります。データベースのメンテナンスなどを除けば利用できない日は基本的にないので、必要になったときにいつでも利用できるのは利用者にとっては非常に大きなメリットだと言えるでしょう。
電子図書館のデメリット
運営側のデメリット:導入コストが大きい
電子図書館サービスの導入には、書籍の電子化が必須です。しかし、書籍の電子化には大きなコストが必要なので、導入のハードルが高くなってしまうのが電子図書館サービスの大きなデメリットです。
利用者側のデメリット:貸し出し可能な電子書籍の冊数や端末の数が足りない
海外では電子図書館サービスが大幅に普及しているのに対して、日本国内の電子図書館サービスはまだまだ発展途上。そのため、貸し出し可能な電子書籍の数・種類や利用可能な端末の数は十分ではありません。パソコンやスマートフォンを持っていない人に貸し出すための端末の数も限られているので、紙の書籍に比べると電子図書館サービスはまだ不十分と言わざるを得ません。
種類別から探す図書館システム
所属している図書館をクリックしてください。