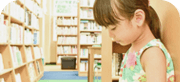図書館のDX推進
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
図書館のDXとは、図書館のサービスや運営においてデジタル技術を活用して革新することを指します。本記事では、図書館DXを推進する利点と課題を解説し、実際に行われている推進事例をご紹介します。
図書館のDXを推進するメリット・デメリット
利用者の利便性が向上する
例えば、図書館の書籍を電子書籍化すると、利用者は図書館に足を運ばなくても、自宅からいつでも電子書籍を借りて閲覧できるようになります。書籍を電子化することで、複数人が同時に閲覧することも可能です。また、音声で図書を検索できるシステムを導入すれば、機械の操作に慣れていない人でもスムーズに目的の書籍を探せます。図書館のDX推進は、利用者の利便性向上に寄与します。
図書館運営業務の効率化につながる
図書が電子化されれば、書籍の管理にかかる時間と手間を削減できます。また、貸出状況をデータで管理できるようになると、運営業務を効率化できます。利用者の利便性向上とともに、図書館の運営効率が向上する点も重要な利点です。
導入費用がかかる
長期的には、ペーパーレス化や人件費削減などの理由から、図書館のDX推進はコスト削減に貢献します。しかし、導入時に費用がかかる点はデメリットです。導入するデジタル化の内容によっては、多額の費用がかかる場合もあり、予算確保が難しい自治体では導入に踏み切れないことがあります。
図書館のDX推進事例
AIを活用して図書検索を効率化
図書検索にAIを活用して、検索作業を効率化するシステムを導入している図書館があります。利用者が質問を入力するとAIがキーワードを抽出し、図書システムが検索を行う仕組みです。図書システムを介することで回答の曖昧さを減らし、より根拠のある回答を提供します。
セルフ貸出機を導入して運営業務を効率化
セルフ貸出機は、多くの図書館で導入されています。画像解析AIデータベースと連携し、利用者が借りたい図書を貸出機に置くと背表紙画像を識別して貸出処理を行う仕組みです。また、バーコードを使用して貸出処理を行うこともできます。
バーチャル書架でより資料を探しやすく
都立図書館では、バーチャル書架を導入し、本棚を眺めるように図書検索ができるサービスを提供しています。図書館内や自宅など図書館外からもインターネットを通じてバーチャル書架を利用できます。
図書館のデジタル化でさまざまなサービスを提供
国立国会図書館ではデジタル技術を活用し、利便性の向上を図っています。書籍の電子化をはじめ、インターネットを利用して資料の閲覧やコピーを行えるサービスなどを提供。読書バリアフリーの推進や情報資源の拡充を実施し、利用者の多様なニーズに応える取り組みを進めています。
図書館システムを活用してDXを推進しよう
図書館のDX推進には初期費用が必要ですが、利用者と運営者双方にとって利便性を高める多くのメリットがあります。図書館のDXを進めることで、充実したサービスを利用し、提供できるようにしましょう。
以下のホームページでは、図書館のシステムについて幅広い情報を発信しています。こちらもぜひ参考にしてください。
図書館システム・会社一覧と
選び方のポイント
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。