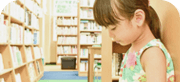システムライブラリアン(システム司書)
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
今、図書館を中心に「システムライブラリアン」が注目を集めています。システムライブラリアンとは具体的に何をする職業なのか、なぜ需要が伸びているのか、どうやったらなれるのか、詳しく解説します。
システムライブラリアンとは
システムズライブラリアンとは、図書館の情報システムを中心に、パソコンでのシステムに特化した司書を指します。
ただし、このシステムライブリアンについては、職業としても位置づけにしても未だ曖昧なまま。コンピューターに詳しければシステムライブリアンになれるのか、それとも図書のことを理解した上でコンピューターの操作にも長けていなければならないのか、厳密な定義は定められていないのが現状です。
司書は「図書館法」にて定められている資格で、図書の保存・整理などの事務を取り扱う職業です。日本に置いてもこの司書の仕事はかねてより存在し、図書館になくてはならない職業となっています。
しかし、かつては全て手作業で行われていた司書の仕事にパソコン業務が加わるようになりました。現在では、図書館での業務の多くが情報システムに依存しています。図書館も小規模なものから大規模なものまでさまざまで、特に図書館が大きくなればなるほど、現代ではパソコンを使った情報システムによる管理が不可欠になってきました。そこで、システムの扱いに精通したシステムライブラリアンに注目が集まっているのです。
システムライブラリアンになるには
日本において厳密な定義は定められていないシステムライブラリアンですが、なるためには、まず司書になる必要があります。その後、各図書館で既存の職員の中からシステムライブラリアンとして任命されることが多いようです。
現在は情報システムに対し知識が豊富な司書も増えてきてはいますが、中にはパソコンそのものが苦手だという人もまだまだいます。ただ、司書の仕事においても、情報システムへの知識とパソコンスキルはますます求められていくことが予想できます。今後は司書の仕事も、誰かが任命されるのではなく、全員が情報システムへの知識が求められるような職業になるかもしれません。
こうしたことから、システムライブラリアンについて知っておくこと、目指すことは、司書として将来を考えた際に非常に重要な要素になると思われます。
資格は不要
システムライブラリアンになるためには、現在のところ司書の資格以外に認定制度などはなく、特別な資格は不必要です。
それなら誰でもなれるのでは……と、思ってしまう人もいるかもしれませんが、むしろ逆です。資格取得を目指すための教室がないということは、全て独学で行わなければならないからです。
システムライブラリアンのスキルを習得するには相当な学習が必要となるでしょう。
システムライブラリアンを目指すなら、もちろん情報システムについての知識と技術は欠かせません。
司書資格と合わせて、基本情報技術者試験やマイクロソフトオフィススペシャリスト資格(MOS資格)に受かるぐらいのスキルが求められます。
基本情報技術者試験はIT業界で働く人が受ける試験のことで、マイクロソフトオフィススペシャリスト資格はWordやExcelなどのアプリケーションソフトを使いこなせるスキルを証明する資格です。
システムライブラリアンの役割
図書館データベースの更新
システムライブラリアンの重要な任務のひとつに図書館データベースの更新あります。
データベースとは、コンピューターやネットワークに大量保存されているデータを検索しやすくしたもののこと。図書館に例えるならデータベースは本棚や書庫です。どんなにたくさんのデータ(本)を所有していたとしても、その中からすぐに目的の本を見つけ出せなければ意味がありません。そして、データが膨大になればなるほど、目的の本は見つけにくくなります。
日本だけでなく海外も含めて、本は毎日、たくさんの新刊が発行されています。こうした本を新たにデータベースに加え、整理や分類するにはデータベースの更新が必要なのです。同時に、バグと呼ばれるコンピュータープログラムの誤りへの対処や、メンテナンスやアップグレードをすることも不可欠な役割となります。
システムを用いた図書館利用者支援
システムライブラリアンは、図書館システムを用いて図書館利用者支援も行わなければなりません。
現在は図書館の中に利用者が蔵書検索を行えるパソコンを設置しているところも数多くあります。
また、図書館のサイトにアクセスすれば、遠方まで足を運ばずとも近くの公民館まで図書を届けてくれるサービスや、予約を行えるところも。
さらには、ほかの地域の図書館と連携して蔵書検索ができるなど、利用者が図書を検索しやすい配慮が行き届いています。
こうしたシステムを用いた図書館利用者の支援も、システムライブラリアンの仕事です。
他の図書館職員へのトレーニング
システムライブラリアンの大切な仕事として、ほかの図書館職員へのトレーニングがあります。
世の中の多くの仕事において欠かせなくなってきた情報システムですが、中にはパソコンそのものが苦手だという方がまだまだたくさんいます。加えて、情報システムの管理などは高度なスキルが求められることも多く、操作方法や仕様も異なっていることから、ほかの職員がなるべく使用できるような状態にしておくのが理想です。
例えばシステムライブラリアンが何らかの理由で休むことになった場合には、ひとりだけで管理していると図書館データベースの更新が滞ったりと、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。
セキュリティ面の管理
情報システムの管理において、頭の痛い問題は不正アクセスなどの悪質行為です。万一、不正アクセスを許してしまえば、最悪の場合にはデータベースを荒らされたり、サイトを書き換えられたり、利用者の住所や氏名など個人情報が流出してしまいかねません。
そこでシステムライブラリアンは、不正アクセスを防ぐため、セキュリティ面の強化を日々更新していく必要があります。アクセスログは最低でも月に1度は行い、利用状況を把握しておきましょう。不正アクセスへの対処のため、時にはサーバーのセキュリティ強化も望ましいです。
システムライブラリアンの育成に向けた動き
インターネットが普及し、電子図書館が広まるなど図書館の新たな可能性が見出されている昨今、システムライブラリアンの需要も年々高まってきています。
筑波大学や慶応大学では、システムライブラリアンのニーズを見込み、現在、図書館に勤務している職員や司書を対象に、情報学を学べる場を提供しています。
しかし、システムライブラリアンの育成は、始めたからといって今すぐにできるもの・なれるものではありません。情報学を学ぶのも、司書の資格を取得するのにも時間がかかるためです。
とは言え、情報化社会が進んでいく中で、システムライブラリアンの育成をただ黙って待っているわけにもいきません。そこで、図書館目線でできることとしておすすめなのは、まずは使いやすいシステムを選ぶことです。
その上で、システムライブラリアンの育成を待ち、人材の獲得を目指しましょう。
図書館システム・会社一覧と
選び方のポイント
種類別に探す図書館システム
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。