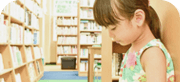図書館システムにおけるICTの活用法
おすすめの図書館システムを種類別にチェック
公開日:
|更新日:
2021年は、教育分野でオンライン授業導入が進んだことから、「ICT元年」と言われています。ここでは、図書館におけるICTの活用法を紹介します。
ICTとは?
ICTとは、「Information and Communication Technology」の略で、情報通信技術のことを指します。たとえば、SNS上でのやりとりやネット通販、チャットなど人同士のコミュニケーションの手助けも該当します。
同じような意味の言葉にITがありますが、ITは「情報を効率的に処理できる技術」を指すのに対し、ICTは「IT技術をどのように活用するか」に重点を置いている違いがあります。ICT技術は、介護や教育・医療分野で多く導入されていますが、近年は農業や建築分野においても、推進が図られてきています。
図書館におけるICTの活用法は?実例から解説
情報端末を使った授業
東京都小金井市の中央大学附属中学校・高等学校では、6学年のほとんどの教科が、校内の図書館を利用して授業をおこなっています。図書館内には、パソコン85台、プリンター21台が設置、壁面スクリーンも活用されています。
2006年には、無線LANも敷かれ、「1人1台端末」が実現。複数クラスの授業が同時に実施されることも珍しくないようです。情報端末を使用しての図書館での年間授業利用時間は約800時間とのこと。ICT導入後、250時間から800時間へと急増したのは、まさにICT環境の整備が関係しているといえます。
また、教室内でも情報端末を使用した授業がおこなわれており、生徒は授業中に自身のスマホや端末を使いながら学習しています。今後は教室も「1人1台端末」を導入する方向で検討されています。
電子書籍の導入
埼玉県立浦和第一女子高校では、電子図書館サービスを開始し、電子書籍の貸出がおこなわれています。大学受験を控えた3年生から、「家庭学習期間中であっても自宅からその場で同サービスを利用し、本を借りられる」と喜びの声が寄せられているようです。
また、浦和一女の電子図書館では、電子書籍の導入にあわせて館内の蔵書検索サービスもバージョンアップ。マイページがあり、自分が今借りている本、予約している本の確認ができます。
学校内には、文部科学省が推進するICT教育を実現していく構想、いわゆる「GIGAスクール構想」の一環として、Wi-Fiスポットが設置されており、校内のどこにいても図書館の蔵書や授業で活用するデータベースなどの検索が可能に。検索場所を選ばないため、探究活動にも役立っているとのことです。
地域情報の発信
茨城県伊奈町立図書館では、地域の情報発信として、「新聞記事に見る伊奈町&TX&合併」「TX&伊奈町行政情報&合併情報コーナー」の作成や設置・運営がおこなわれています。ホームページを開くことで誰でも閲覧が可能なため、この事業が展開されて以降、自身で館内のインターネット端末を利用し検索する利用者が増加。
「雹(ひょう)による農作物への影響はどうか」「TX(つくばエクスプレス)の開業前後では地価がどの程度変化したか」といった地域関連の問い合わせも増え、地域情報の収集・発信に役立てられています。
無線ICタグの活用
岩手県江刺市立図書館では、無線ICタグによる図書館サービスが導入されています。図書館システムとICタグ(バーコード併用)により、これまでの図書カードによる管理と比べて、貸出返却業務・蔵書点検が迅速かつ正確な対応が可能に。
また利用者からは、自動貸出機について、「自分で借りられるのがいい」「便利」という声、カウンターにおける貸出・返却について「1度に数冊の図書を読み取れる」「手続きが早い」といった声があがっています。
電子図書館システムの制作
岡山県立図書館では、電子図書館システム「デジタル岡山大百科」を作成し、県民に岡山県立図書館資料を提供しています。
同システム内では、総合目録ネットワークである「岡山県図書館横断検索システム」や資料の本文やコンテンツの内容を視聴できる「郷土情報ネットワーク」など3つの機能をメインとして展開。「郷土情報ネットワーク」では、メタデータによる情報管理がなされているため多彩な検索が可能となり、探究活動に役立てられています。
情報発信コンテンツの作成
千葉県光町立図書館では、図書館が地域の情報拠点となるために、ホームページによる情報発信がおこなわれています。発信内容は、季節のできごとやニュース記事、図書館の行事と関連した所蔵資料などが中心。
またメールマガジンも配信しており、新刊書の刊行予定や新着資料の案内、行事案内や図書館からのお知らせなどが掲載されています。今後も、ホームページを軸とした「地域の情報拠点としての図書館運営」が目指されています。
種類別から探す図書館システム
所属している図書館をクリックしてください。
種別ごとに、導入数が多い図書館システムを2つ以上掲載しています。